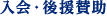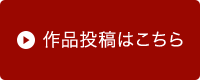日本現代詩人会 詩投稿作品 第37期(2025年4月―6月)入選作・佳作・選評発表!!
厳正なる選考の結果、入選作は以下のように決定いたしました。
■伊武トーマ選
【入選】
石塚ちえ「ルッカ ルッカ バブーシュカ」
小川あう「catch row」
緒方水花里「I will bone」
嶋田隆之「窓とケヤキと」
ゐで保名「釘」
【佳作】
清澄健二郎 「はぴばあすでい」
宮本誠一 「蝦蛄」
ユノこずえ 「隣人とピラカンサ」
鈴木日出家 「踏切」
中島悠惺 「知った」
■橘麻巳子選
【入選】
緒方 水花里「廃品」
小倉俊太郎「虎」
姜運(カンウン)「木曜日」
未補「Unbloom」
【佳作】
三明十種「夏空度數」
永井雨「洗濯機、スペース」
田中傲岸「暮れる」
牟呂弓矢「ひとつの町」
■根本紫苑選
【入選】
蝸牛「クビキリギス」
遠野一彦「せんたくのそねっと」
ユノこずえ「隣人とピラカンサ」
赤石治「Crying substance」
ゐで保名「釘」
【佳作】
浅霞なせ「生きることの距離」
信田森「揺籠」
嶋田隆之「窓とケヤキと」
清澄健二郎「はぴばあすでい」
姜運「木曜日」
投稿数 708 投稿者 388
沢山のご投稿ありがとうございました。
引き続き、皆様のご参加をお待ちしています。
石塚ちえ「ルッカ ルッカ バブーシュカ」
逢瀬を跨いで
空洞の薔薇の底知れぬ鈍群青の生塊
バブーシュカは 百年の恋を呪う
麒麟の伸ばしすぎた爪先に
バブーシュカの嬌声が球体に化けて 霧散する
赤子のまま大きくなった
飢餓の明滅珊瑚礁
バブーシュカ
ルッカ ルッカ バブーシュカ
「水面を果てた 波紋の呼応が永遠に私の腹部で律動を繰り返している
わたしは 鉱物に閉じ込められた 三つ指の子宮なのですね」
わたしの三つ指が揺れる
揺れる
揺れる
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、
割、、、、、、、れ、 る、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、
、、、、
、、、、、、、、、
、
、、
、、、、、、、、、、、、、
、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、
、、
水面は静寂すら裏切る 黙秘の庭だ
割れた百年を バブーシュカがくすねる
飢餓を産卵する 生まれたままの
五百年を生きたバブーシュカ
その身に落ちた デルフィニウムの血には
さびた六月の風が
「バブーシュカ
お前の心臓を見たよ
四角体に五カラットのダイヤを数百埋めた
日に透けた黒鍵が震えるね
呑んだ蜂が暴発するんだ
空洞と目が合った
愛おしい飢餓だよ バブーシュカ
爛れるほどの地面で見上げた空の美しさに
残酷な賛美にカラカラに乾いた唇をひとつになるまで結んで」
バブーシュカ
ルッカ ルッカ バブーシュカ
白濁の脱色でシリアルピンクに禿げた
頭部を持たないバブーシュカ
君が集めた蜂の山はがらんどうの球体だ
楕円に切れて大穴を抱えた 虫の果て
ルッカルッカ
バブーシュカ
リクベルベット チルチット ルッカルッカ
群像蟻の王は
流星が目を合わせるとちぎれてしまうことを知っている
それは呼応だよ バブーシュカ
渇望を叫んでいるんだ
途方もない
何もできない君に唯一 聞こえる
子守唄の永遠だ
ルッカルッカ
檸檬の破水を知らない……
ルッカルッカ ….
赤子なき揺籃の氾濫…..
ルッカ ルッカ ………リクベルベッド
チルチットルッカルッカ….
ルッカ、ルッカ、 バブーシュカ、
小川あう【「catch row」
かさかさの風が吹く中旅に出た
とたんに家に帰りたくなった
柔らかい髪にかけるドライヤー
小さいおしりが膝に座っていて
でももうリュックを背負ってしまったから
脱げない靴を履いてしまったから
楽しいテレビは終わってしまった
そして私は目薬を差した
靴を板に打ち付け
私は目を瞑って決めた
もう戻れないけれど
どの道誰も戻ることなどできないのだし
目を開けパンを食べる
河の幽霊に足を引かれるのは
いつだって私じゃない
楽しいテレビは終わってしまった
後向きに進んでいく
私は競技用ボート
誰にぶつかるかも分からない
真っすぐ進んでいるかも分からない
見えるのは私の家だけ
背中を丸くして授乳する私
どんどん遠ざかるのが見える
そうやって進んでいる
背中を反らせて漕いでいく
水を掴んで離す
母のことを少し思い出した
ミシンや赤や緑のまち針のことを
火葬場の煙は細く伸びつばめがびゅんと切った
そんなこともどんどん遠くなっていって
でもまだここは旅の序盤だという
もう針の先ほども見えなくて
でも見えている
私にしがみついて眠っていた可愛い子ども達
煙が千切れ繋がる
晴れてる
緒方 水花里「I will bone」
月のリズムが欲しくってペットショップに行ってもなかった
仕方がないから銀の匙を買い遠くの月を乗せてみるけれど
そういえばシリアルは小指でしか食べたことがなかった
オートミール(自動化された食事)
小さなヨーグルト1つの食卓で
少女は回らない
月の砂
理科準備室で恋をした
背の高く落ち窪んだ目で
あなたの首が
にくづきでないと
わかった瞬間
薬匙からこぼれ落ちた
肋骨を木琴にして叩く
骨のリズム。それは回らない。空中ブランコから垂れる経血の夢。
骨のリズム。喉仏。歩く度にコツコツと鳴る爪先と松葉杖。
僕には当然生理はなく、生きる理もなく、彫刻刀で体を削る。
満ち欠けしてはならない。欠け続けなければ、鋭い、それで快い
骨のリズム
現代、ブルーライトの時代、月の光による影響はないように思える
だが僕らはBluetooth1つで簡単に同期され、環状線は月のリズムで
揺れ動いてはまた元の場所に落ちる
君もそうなりたい? 蹲る背中に話しかける、円環の切れた肋骨
理科準備室には逃げて来た。家では父が豚肉をスライスする
丸くて白い脂肪は盾であり、つまりそれに幾ら焼印を入れても
また戻りたいかい?
少女は逆立ちをした。体内から砂が落ちバッグはもう、持たない。
あなたになりたい
恋とはつまりそれ
あ焦がれで自分を殺すこと
あなたと同じ見られても
静物と立っていられる姿を!
カタカタ
首から下の
月を切り開けば
羽になる
あなたは大腿骨を手に取り
穴を開け無息を吹き込んだ
骨のリズム。怪獣の背鰭。蹲る凹凸が僕をどんどん「僕」に変える。
骨のリズム。蝶番よ軋め。2つに割れた月は天使の羽と呼ばれる。
僕は軽くなる。
鋭くなる、
もう満ちない月が胸の中心をにゅっと貫き、白い一つの鎌になる、
死神だね、
Cellulu(セルラ)、Cellulu(セルラ)、Cellulu(セルラ)、Cellulu(セルラ)、ite
鉱物が何処にでも転がっている、ベビーカーにも山手線にも
ほんのわずか残る僕の少女にもite、ite、itai、お願いitaiうるさい、
僕は胸の肉付きを切り、全ての光を断ち切り、ただの白い歯、自ら
母でない
骨格標本になる
溶鉱炉(オーブン)の準備は出来ている、回らない、
真っ直ぐに一直線上に
嶋田隆之「窓とケヤキと」
屋根もベランダも重機で崩され
便器も玄関の扉も廃棄物トラックに放り込まれ
小さなアパートはなんにもなくなった
最後に油圧シャベルは
窓の外に立っていたケヤキを抜いた
根っこから掘り起こされたケヤキは
なんにもない地面に転がされた
そこには窓があった
いつもケヤキが覗き込んでいた窓があった
窓の中では
初めての日に若い妻が危なっかしくハンバーグを焼いた
寝つかない娘の横で若い父親が白い天井にため息をついた
でももう なんにもない
誕生日のたびに増えるおもちゃをしまった押入れもない
いつか手渡そうと夫婦で整理したアルバムを並べた棚もない
娘が撮ってくれた夫婦二人の写真を置いた下駄箱もない
本当になんにもない
そこには窓ができるという
小さなマンションが建つという
窓からは
慣れぬ手つきで味噌を溶く男性が見えるかもしれない
真夜中の赤ん坊の泣き声に灯る明かりが見えるかもしれない
部屋を這い回る幼子を追いかけるスマホが見えるかも知れない
繰り返されるかもしれない
新しく始まるかもしれない
ケヤキがいなくても
そこには窓があった
窓を開ければすぐ前にケヤキの木があった
春には若緑の小さな葉っぱを揺らした
いっぱい揺らした
リビングの窓を額に、それは一枚の絵になった
カーテンを全開にして眺めた
そんなに開けたら外から丸見えやんか
そう言う妻も笑って隣に座り
窓の外を ケヤキを見た
今も見える気がする
そんな気がする
ゐで保名「釘」
壁に、釘が、一本。
錆びている。
これは、
誰かの、意志の、化石だ。
何かを、ここに、留めようとした、
遠い、昔の、熱の、残骸だ。
打ち込まれた時の、
壁の、痛みは、
もう、乾いている。
釘は、
壁と、一つになることで、
痛みから、解放されたのか。
それとも、
痛み、そのものに、なったのか。
時は、
この、釘を、避けて、流れる。
この、一点だけが、
永遠の、午後に、取り残されている。
もし、
この、釘を、抜いたなら。
壁は、
傷口から、
何を、流すのだろう。
血か。
砂か。
それとも、
ただ、溜め込んでいた、
膨大な、沈黙か。
俺は、
その、釘を、
ただ、見ている。
俺も、
誰かの、意志によって、
この、世界の、壁に、
打ち付けられた、
一本の、
錆びた、釘なのかもしれない。
緒方 水花里「廃品」
ホルモンはうちの臍の緒
放るもんっちいう意味やって
夕焼け血の中泳いで来る
ほおるもん、ほおるもんありませんか
マルチョウが一番やね。牛の小腸を裏返して
膜ん中アブラがギシギシ詰まっとる
餓鬼に似とるね
マーガリンばそんまま食いよる
母親がおった時はよーマルチョウ食えたんやけど
うちでは鍋が煮え もつは栄養満点やけん
食べり
母親はうちを捨てて別の男んとこ行った
うちはコロコロコミックを何度も何度も拾って帰った
そのたんびに父親に殴られた
デブ、ブタち竹刀ば振られた うちはマーガリンば食うた
愛とは与えるものならば
食卓には何もなかった 鍋も
少年漫画の中にも
父親から離れた街でゴミ捨ては夜やなくて朝やった
うちはマルチョウ1kg抱え夕焼け血の色走り抜けた 火ば点け
鍋ん中具ツラ愚面地獄ん中可愛く開く赤ん坊
父親ん指
詰まったアブラが白い花ごつ
人間マルチョウが一斉に煮えたぎる
食らう
父親をバラバラにして啜る
食らう
歯の間でプツプツと死ぬ 食らう
たらふくたらふく食うてから
うちはうちを裏返す
うちはうちを裏返す
口ん中から小腸と食道がそんまま出る アブラんギシギシ詰まって
うちはただん管
うちはただん内臓
内臓の中逆流して出て来る
マルチョウショウチョウレバーハツセンマイデブブタコロコロコミックうちんはらわたうちんはらわたうちんはらわた
うちん臍の緒まで到達する 小腸と食道と繋がってピンと張る
うちは一本の内臓
から反吐を吐く血反吐を吐く血も食べたもんと一緒なって出て来るトイレん中何もかんも吐く廃品回収の車が通る
たらふく持ち帰った給食の余りのパンもほおる
母親の産まれんかった腹違いの子もほおる
でもまだ足らん食らう食らう吐くうちは時間をほおる金をほおる
命ばほおる
マルチョウのマーガリンの父親の母親のうちんはらわた
うちはうちを食べるそれすらも吐き出しどんどん痩せてく涙を吐く体が動かん
うちはもうデブやない
うちはもつ、かれたわ
天神コアの屋上からほおったら
フッと
風になって
うちいっちゃん軽くなった
真下に見える血の車
ほおるもん、ほおるもん
小倉俊太朗「虎」
目の前に虎がいるとします。
いや、いないんですけど。
いるとします。
虎は大きく口を開けて、ねばっこくまとわりつく匂いが虎の口の中から漂ってきます。
これがサバンナの匂いなのでしょうか。
通りかかった熱力学の教授が「ですからジャングルです」と言います。
私は赤面して、その場にうずくまって、耳を塞ぎました。
ここで、虎だけでは足りないので保育士にやってきてもらいます。
保育士は、水筒を持って私の後ろに立ちます。
前門の虎、後門の保育士です。
保育士は裸体にエプロンをかけていて、布が薄いので体の起伏が布の上からでもよくわかります。
春ですね。
庭の桜はすでに散って、ツツジがぽつらぽつらと咲き始めました。
今から一ヶ月前に庭にある一本の木に白い花が咲いていて、その花の名前をGoogleレンズで調べようと思っていたことを思い出しました。
記憶上のそれに何か名前をつけましょう。
F値。
F値は怠惰と起床のサイクルに苛まれていたそうで、大雨の日には上流から鯨が流れてこないかと水位が増した近所の川を見に出かけました。
川上から鯨が流れてきたとします。
いや、こないんですけど。
来たとします。
鯨は大きく口を開けて、乾燥していてさっぱりとした空気を私に供給しました。
円安でガソリン代が上がっていた私にとって、それはこの上ない幸福でした。
通りすがりの人類学者が「鯨の吐息はエネルギーを生み出さない」と言います。
私は彼の無知さに驚愕しました。
その程度の知識のなさでよく学者を名乗れたものです。
私は彼から学者の称号を剥ぎ取りました。
自由から生まれた行動にはその結果に対する責任が生じます。
私は代わりに名前をつけなければなりません。
一晩考えたけど何も浮かびませんでした。
本当に一生懸命考えたんですが、何も浮かびませんでした。
私は彼の母親に謝りに行きました。
いませんでした。
姜運「木曜日」
町中がプールの匂いに包まれた日
それはまたたく間に下着まで染み込んできて
心なしかみなが遊泳しているような
ひんやりと 起伏のない顔
少々お待ちくださいの言い方ひとつにも棘を探りあてそうになる
こんなに皮膚が薄いなら生きていくなんて無理じゃないのか
硬い子音を使ってはいけない
うそ すそ つそ ぬそ
口にしてしまうと鬼が形を持ってしまうから
ぬるい子音だけを踏んで歩く
働くことにいちいち傷ついて
つまらないと割り切ることもできない
反論できなかったのはあの人が勝手にロジックを変えたせい
そして大きな声で成否を問うたから
利益を
原価率を
お気持ち代を
ごっちゃにしたから
そんな複雑な計算はできません
自分を痛めつけるように
粉チーズをばしゃばしゃとかける
引っかかる粒をがりっと噛んで
舌の上で弾けた点の痛みに
入っていないはずの黒胡椒だとわかる
今日のところはこれが落としどころなのだ
950円プラス140円プラス376円
鬼を遠ざける飛び石
210円プラス205円プラス110円
鬼から逃げるための飛び石
未補「Unbloom」
十字を切るはずの蝶は、真円を描いた。
祈られるはずの花は、単生のまま、あらゆる悲を覆い尽くした。
二藍に烟る一雨。
一滴のニカ。
落花のなかの息継ぎは、ハトロン紙を裂くような痛みを伴った。
ゆりかごのなかの蛹は、みずからを揺れ、波音は垂直に落下した。
泳いでも、溺れても、ねむりのなかに、足はなかった。
(絵はどこにでも流れつくのに、どこにも無い)
白色の果てには、たくさんの石があるだろう。
あなたは、もっとも清潔で、もっともおそろしい石を選び、くちづける。
つめたい円環から抜け出し、最初の一声を得る。
ようやく水のかたちを知る。
蝸牛「クビキリギス」
「ばあちゃん、何の虫が鳴いてるの?」
「クビキリギスだよ。噛まれたら飛び上がるほど痛いから気をつけな。身がちぎれても、首だけになっても噛みつき続ける。そんな奴らさ。」
タカシは一年前に両親を失い、故郷を後にした。
今は祖母のフミエと二人きり。屋根には古びた鯱が睨みを利かせ、
この家もフミエも、タカシにとって唯一の拠り所だった。
ある日、学校から帰ると、飼育ケージにクビキリギスがいた。
フミエが自由研究用にと、捕まえてくれたのだ。タカシはケージ越しにそいつを凝視した。その印象的な真っ赤な大アゴに、思わず目を背ける。
朝、目が覚めると、隣家の屋根が地面に散乱し、テレビは地震一色だった。
「鯱のおかげかねぇ…」
力なく指差すフミエの視線の先、我が家の屋根は、鯱が屋根を噛み締め、無傷で聳え立っていた。
その時、ケージから飛び出たクビキリギスが、タカシの指に食らいついた。慌てて引き離そうとすると、そいつの躰がちぎれ、赤い首だけが指に残った。タカシは、滲む血を見つめながら、その痛みを、ただ深く抱きしめた。
遠野一彦「せんたくのそねっと」
まいにちまいにちあめふって
あおぞらみえたらせんたくします
まいにちまいにちあめふって
あおぞらなくてもせんたくします
しろいしたぎやはながらぱじゃま
よごしたおしもにきたないおくち
まいにちまいにちせんたくします
こころのなかでせんたくします
しかくいまどからみえるそら
はれてくもってあめふって
そらのせんたくまいにちします
わたしのからだはねたままで
こころのなかにあめがふる
あおぞらみたくてせんたくします
はじめがあると
おわりがくる
おわりがくると
はじめがはじまる
たった93年間を生きた隣人の男性が
おわりを迎えそうだ
先月までは日曜日ごとに
おしゃれなハンチング帽をかぶり
競馬場におもむいていたのに
長身の彼は若いとき
映画俳優をしていたこともあったらしい
風がおしえてくれた
何かがはじまりそうだが
今はなんの兆候もない
救急隊員二名に抱かれてアパートの
階段をおりていった
わたしは
動揺しながら
頭のなかで
彼を永遠に見送るべき手順を準備していた
そのあとしばらく茫然とする
彼に嫌な感情を持ったことは一度もない
関わりのない見事な隣人だった
なぜ
ここまできたのに
歳をとり弱り存在が消されるのかわからない
このまま
しずかに穏やかに永遠に
隣人として生きてくれればよいのに
何もはじまらなくてよいのに
何もおわりにならなくてよいのに
ニ月の寒さの底に
アパートの庭のピラカンサの紅い実を
食べ尽くすヒヨドリたちの群れが
終日にぎやかだ
ただ
そのなかの一羽が
ピラカンサの木のこずえに留まりつづけ
しげしげとわたしを見下ろしていた
わずかに寂しさをいやされたのだった
赤石 治「Crying substance」
染色体の数だけ細胞は泣いて心臓を作ったのかもしれない
心臓という物質の中できみの泣き声はやがて鼓動となった
でもきみには欠落した染色体があったから足りない分だけ
他の人より多く泣かなければならなくてその小さな心臓は
きみが自分自身になるために幻の染色体に向けて脈搏った
物質はいつも泣くことによってはじめて物質になっていく
それは泣き崩れるように自分自身を思い出して物質になる
あの空は青くなるためにどれだけ悲しみを集めたのだろう
空が切り抜かれそこに鳥の線が描かれるとき欠けた中空に
時間の断片が補われて空は青い傷の中で鳥たちを思い出す
たとえばあの鳥は以前から羽ばたき鳴いていたはずなのに
その時はまだ鳥ではなくて空と区別できない悲しみだった
回想の中でわたしたちは鳥になり鳥はわたしたちになった
悲しみは物質から過ぎ去った時間を吸い上げて泣いている
あの海はどれだけ涙を流して自らに深さを刻んだのだろう
波の間で砕けた光がきみの欠けた染色体をただ映していた
この大地は誰もが眠るためどれだけ苦しみに耐えただろう
土がくり抜かれそこに石の形が彫られると時間が鋳造され
生きた時間と死んだ時間が交わってあなたの色彩になった
たとえば年老いた石も以前から大地の底で眠っていたのに
その時はまだ石ではなく大地と区別できない悲しみだった
石は泣きながら自らを静かに思い出して物質になったのだ
石の夢の中で大地から空を見上げるとそこでは見覚えある
わたしたちのような鳥が飛んでわたしたちを回想していた
どれだけ泣いたら愛はこの胸で物質になるのでしょうかと
きみは生まれる前に失くした染色体に語りかけて涙を流す
その言葉は物質と時間の間できみの名前を思い出している
きみはいつも人にうまく言葉を伝えることができないから
為す術もなく泣き崩れ言葉から言葉の形を逃がしてしまう
きみは自分自身になるために泣き止まない時間の中にいた
もしも愛もまた泣くことによってはじめて愛になるのなら
きみの涙は欠落した染色体を補うように時間を編み上げる
その糸で織られた心臓はきみの名前を深淵から呼び続ける
時間もまた泣くことによってはじめて時間になるとしたら
わたしも泣いて時の彼方へ消えた最初の言葉を連れて戻り
どんなに愛しているかを細胞の数だけ言葉にしていきたい
その言葉は鳥となり石となりわたしたちとなり鼓動を搏ち
物質から聞こえる生と時間から聞こえる死の同じ夢をみて
幻の染色体に抱かれて今も生まれた日のように泣いている
泣くことはきみがきみ自身になるための最初の航法だった
鳥はあの空に石はこの大地にきみは遠い時間の中に刻まれ
欠けた染色体の代わりに愛に泣き続けてその心臓を満たす
そしてきみの涙は物質と時間を繋いでこの世の色彩になり
すべての愛が泣きながら互いを回想する鮮やかな世界の中
きみはその小さな暖かい鼓動と共に永遠に自分自身になる
【選評】
■伊武トーマ 選評(37期全体)
今期も世代を超え多様な作品が寄せられました。作品と対峙しながら、詩に対する思い、考え、姿勢も、ずいぶん多様化しているなと実感しつつ、今期は、思いや考え、姿勢を表現するものではない作品を選びました。物理学者が言う「数式は、空中に漂っている」が如き世界共通の記憶というか、自分自身以外の何者か… 外部から侵食して来る何者かによって、自身が媒体となり、あたかも言葉を紡いでいるかのような… そんな作品を入選にしました。佳作については、豊富な経験を積んだ作品を中心に、フレッシュで可能性を感じる作品を選びました。
【入選】
■ 石塚ちえ「ルッカ ルッカ バブーシュカ」
一連、一連が三次元を平面化し、奥行きがあるように再構成した、ロベール・ドローネのタブローのようでした。連と連の余白にさらなる奥行きと息遣い、響き合う色彩とタッチを感じ、さながら言語による現代アート作品といったところでしょうか…
■ 小川あう「catch row」
柔軟なようでいて言葉のエッジが立ち、硬質な行と行のぶつかり合い。緊張と静寂が互いに引き合いながら、リアルな異世界が表出されていて見事です。連間に音もなくスパークする白熱… 思わず「catch row」と唸ってしまいました。
■ 緒方水花里「I will bone」
意味と意味が互いに牙を剥き、解体し、跳ね飛ぶ言葉たちが、草間彌生の水玉のようにリズム感たっぷり、無限増殖して行くかのようです。とてもポップな作品でありながら、実存の闇が随所に現れ、こちらも現代アート、言語による造形作品という感じです。
■ 嶋田隆之「窓とケヤキと」
窓を介して視点が逆転する手法が良かったです。窓の外側と内側が交差し、次第に過去と現在が重なって行きます… いつとも知れぬ時空に迷い込んだ読み手が、鏡の前に立ち、「どっちが実像なのか?」と問いかけているかのような読後感… ルネ・マグリットが描く、形而上的世界観を想起しました。
■ ゐで保名「釘」
本当に釘を壁に打ち付けているような… 触覚があり、質量がある言葉たち。釘打つ言葉たちは時を刻み、刻まれた時は傷となって、自分自身に跳ね返って来るかのようです… 心臓にとどめの一撃をもらわないよう、詩人はうまく我が身をかわさねばなりません。
【佳作】
■ 清澄健二郎「はぴばあすでい」
時間軸が逆転しながらもパースを立ち上げて行く、高い技量… 最終行「はぴばあすでい」により、天使の羽が如きポエジーが舞い降り、あたかもカタルシスの光に、全身が洗われるかようです。
■ 宮本誠一「蝦蛄」
頭の中ではなく、五感全部を使って詩空間が構築されていて、才能を感じました。あるべき位置に「蝦蛄」の一語がぴったりはまるのも見事。詩人ならではの第六感ですね。
■ ユノこずえ「隣人とピラカンサ」
最終連のヒヨドリたち… 一気に視点が切り替わり鮮やかでした。ピラカンサを介し、私と隣人、都市の孤独を浮かび上がらせていますが、ヒヨドリの登場で一筋の光が差し込みました。
■ 鈴木日出家「踏切」
心の中の踏切の前に立ち、踏み出せずにいる〝ぼく〟 踏切の向こうの〝学校〟 カンカンカン 踏切の警報音に押されながらの葛藤… 〝光に似た影〟とは、〝詩〟そのものなのではないのでしょうか。
■ 中島悠惺「知った」
リズムを大切にしていて、歌が聴こえて来るようです。連間から若々しい息遣いがして、これからが楽しみです。
■橘麻巳子選評
年間を通しての投稿欄の半分が過ぎました。あと半分です。ファイト!
【入選】(4篇)
■緒方水花里「廃品」
すべてをぶつけたのかもしれない、と感じさせる作品は、ある。作者がそう思っても成立するかは分からない中、この作品には確かに動かされるものがあった。
正気である状態とそうでない状態で引き裂かれそうな「うち」を冷静に観察しきる眼が無ければ、ここまでの完成度には至らないだろう。文字の配置、改行、最後の「ほおるもん、ほおるもん」の締めくくり、どれを取っても作品世界の勝手を知った眼と緻密な手つきが浮かんでくる。
もしこれが〈私〉的な題材であるならば、その観察を止めずに書き続けて欲しい。そして他の題材を扱う際にもぜひ生かしてみて欲しいと思った。
■小倉俊太郎「虎」
冒頭から、わたしたちは仮定の世界を見せられる。「目の前に虎がいるとします。/いや、いないんですけど。/いるとします。」。慎重に念を押しているようで悠々と三行に広がったとぼけ方は、こちらを笑顔にさせるユーモアだ。一方で、作品世界の成立を説明されるよりも早く場面が進行していく。解釈で切り分けられるより前に、読者は先へ先へと引っ張られていくのだ。先部までクロースアップされるように描かれる事物たちは、イメージをぴたりと限定させられている。それは一種機械的で、まさに「Googleレンズ」からもたらされる多くの情報のようでもある。
「私は彼から学者の称号を剥ぎ取りました。/自由から生まれた行動にはその結果に対する責任が生じます。/私は代わりに名前をつけなければなりません。」という三行において、語り手の行動がまさに責任を回収するという仕組みになっているのを面白く感じた。ナンセンスの暴力に隠した、作者の意志のようなものが垣間見えた。
■姜運(カンウン)「木曜日」
敏感な心を表す面の強い作品かと思いきや、三連目にて突如「硬い子音を使ってはいけない/うそ すそ つそ ぬそ/口にしてしまうと鬼が形を持ってしまうから/ぬるい子音だけを踏んで歩く」と異形の行が出てきて驚かされた。
発言としての〈声〉を出す、出せないの間を引き離している現実の出来事が仔細に書かれるほどに、最後まで「遠ざけ」られて現れることのない「鬼」の抽象的な恐ろしさが想像させられる。
最終連の、どこか角ばったような書き方へのこれもまた急激な変化は、形なき不穏なものを不穏なままで漂わせる雰囲気の制作に長けた筆力を思わせるものだった。
■未補「Unbloom」
一瞬で消えてしまうような出来事が、一行ごとに時間の流れを伸び縮みさせ、記録されている。今、〈記録〉と書いた。物語的な展開であるのに、それぞれがどこかフレームに入れられた写真のように感じるのは、二連目までの過去形の連なりの効果だろう。三連目では人間が登場し、ふいに視点に〈生〉が吹き込まれる。
この短い詩篇のなかで、世界を常に動くものとし、壊し、また再生させる作者の技術は高いものと思われる。また、三連目の「つめたい円環から抜け出し、最初の一声を得る。/ようやく水のかたちを知る。」というラストに至るまで、自身の想像をじっと観察したであろう、静かな忍耐に美を感じた。
【佳作】(4篇)
■三明十種「夏空度數」
観念と視覚的現実の間が、その境界すら無いかのように通過される。作品内に登場する「顔」は、夏空の傾斜を「滑り落ち」たり、「拾い集め」られたりする。語り手の頭の中の存在かと思われたものが、文字上で明確に手触りのあるものへ変わってゆくのが、読んでいて化かされるようである。
行空きのない形式もまた、作品の重力を弱めないことに一役買っている。
■永井雨「洗濯機、スペース」
ドラム式洗濯機に背中を付けてその振動を感じる。シンプルな状況を書き込んでいくことで、語り手の思考のまわる様子とのイメージの一致が上手くいっている。行アキのやり方も良い視覚的効果を生んでいた。最後の三連の繰り返しからのズレは、電化製品がしゃべる時の音を思わせ、遊び心を感じた。
「展覧会でジャポニズムを垣間見た」という短い作品とどちらを取り上げるか迷ったが、作者の書く力がよりはっきり見えるという点で「洗濯機、スペース」にした。
■田中傲岸「暮れる」
「くず」という単語が頻出するが、「くず……くず……くず」や「くず……くずくずくず」
とまるで鳴き声かのような4度にわたる書き方の変化が、全体のリズムを格段に良くしている。また、自己を繰り返し俯瞰する観察力はこれからも継続させたら良いと思った。俯瞰視点はともすれば無限の行為にもなりうるが、この作品では、丁度、というところで止められており、「おれに、おれ自身の感性の貧しさに」といった直線的なことばを使った行も生きている。
■牟呂弓矢「ひとつの町」
「開いた口が塞がらないと言うと」「棒に当たって死んだ犬はいなかった」「爪に火を灯して死んだ老婆もいなかった」など、慣用句的表現が多用されることで、昔から馴染みのあるかのような〈型〉を持った物語を作るのに成功しているように思える。詩における慣用句の使用は一種の試みともなるだろうが、この作品ではそれが飽和し、シニカルに感じさせる位まで突き抜けていた。
■根本紫苑選評
【入選】
蝸牛/「クビキリギス」
両親を失った少年、タカシと唯一の家族となった祖母フミエの物語。屋根を噛み締め、地震から家を守った鯱のように、クビキリギスはタカシとフミエを家族として結びつけてくれる。だから、タカシは首が取れても噛み付いたままのクビキリギスが与えてくれる、「その痛みを、ただ深く抱きしめた」。
人との関わりは、よろこびだけでなく、痛みを伴う。その痛みを、クビキリギスのゾッとするほど真っ赤な大アゴや噛まれたときの血が滲むほどの痛みとして可視化している。少年が淡々と痛みを受け入れるところが良い。
遠野一彦/「せんたくのそねっと」
「まいにちまいにちあめふって/あおぞらみえたらせんたくします/まいにちまいにちあめふって/あおぞらなくてもせんたくします」はじめて読んだときは、梅雨時の洗濯って大変だよね〜と思いながら読み始めたが、そんなかわいい話ではなかった。作者と話者の、洗濯する側と洗濯したいけど汚すことしかできない側、つまり介護する側とされる側の視点が混在しているようにも見えるが、それは距離の短さのせいかもしれない。最初から最後までひらがなのみで書かれているが、漢字やカタカナを使わないのは良い選択だと思う。
ユノこずえ/「隣人とピラカンサ」
隣人の男性が救急隊員に運ばれていくのを見て動揺している話者がいる。しかし、よく読んでみると、その男性はまったく関わりのないただの隣人に過ぎなかった。日曜日ごとにおしゃれなハンチング帽をかぶり競馬場に出かけるのを見ていただけの関係。昔のうわさ話を風に教えてもらうくらいの関係。ただ、それだけの関係なのに、話者は、何かがおわり、何かがはじまることを恐れている。作中の舞台は2月、投稿されたのは4月で、ちょうど、年度末と年度初め、すべてがおわりすべてがはじまる時期である。止まっているかのような穏やかな生活に変化が生じて、時間の流れを感じて、恐ろしくなったのだ、と思う。何気ない日常が、いつまでも続けばいいのに、と私も願う。
赤石治/「Crying substance」
「Crying substance」とは、泣く物質、という意味でしょうか。染色体異常による心疾患を患うこどもを持つ親が話者の作品。泣いて泣いて、泣き崩れて、「どれだけ泣いたら愛はこの胸で物質になるのでしょうか」という「きみ」の問いはとても胸が痛い。16連に渡る長い作品で、悲しみと苦しみで満ちている。しかし、泣くことを悲観的に書いているわけではない。「物質はいつも泣くことによってはじめて物質になっていく/それは泣き崩れるように自分自身を思い出して物質になる」。この一連は重くこころに残る。
ゐで保名/「釘」
壁に刺さった、一本の釘に着目して書いた作品。コンマ「、」を多用していて、読むたびに呼吸が途切れてしまうけど、これはきっと釘を打っているのだと気づく。一本の釘をただ見ている自分と、それを詩に書きながら、ひたすら打ち続けている自分がいる。話者は、「誰かの、意思によって、/この、世界の、壁に、/打ち付けられた、/一本の、/錆びた、釘なのかもしれない」が、これを書いている作者は、自分の意志で言葉の釘を打ち続けて、たった一本の釘を作品に仕上げた。
【佳作】
浅霞なせ/「生きることの距離」
わたしという存在への不安、不確かさ、伝えたいことは伝えられない。「言葉のすべる感覚のなかで/ずれていく意識そのものが会話であり/わたしなのだと気づいていく」。個と世界とのかかわりとして、わたしという存在が正しく見えていようがずれていようが、世界から見れば一個人の一生なんて一瞬の出来事にすぎない。国とか地域とか、特定の所属や団体とかで代弁され、個人は、個性は埋もれてしまいがち。「けれどもわたしはあなたではない」この、最後の一行のために、私はこの詩を選びました。
信田森/「揺籠」
生まれることができなかった、さっちゃんの妹のお話。話者はさっちゃんの家族の話をしている「あたし」だが、もしかしたら、大人になったさっちゃんが過去の自分に語りかけているのかも知れない。「さっちゃんのママのママだけが/花束みたいな名前をつけた」「天国と夜のひとつになるときに/パパとママがすきとおること/さっちゃんは知らないけれど」など、小さいこどもに話すように、ひらがなを多用して、やさしく表現している。
嶋田隆之/「窓とケヤキと」
ケヤキが見える小さいアパートの一室、そこから始まった家族の物語は、ケヤキとともに成長して、やがて家族はアパートを去り、アパートは解体され、ケヤキも倒された。そこにまた新しいマンションが立つと、また新しい家族の物語が始まるだろう。その物語はまた、別の木が、別の空が見守ってくれるだろう。アパートもケヤキの木ももうないけれど、思い出の風景にいつも存在する窓の外の一本の木。嶋田さんの「コバンソウ」でも、息子の知らない父と母の思い出のコバンソウを描いている。静かでやさしい語り口は植物のイメージによく合っている。
清澄健二郎/「はぴばあすでい」
たくさんのたくさんのさようならを経て、たくさんのたくさんのたましいが想いあい、引き合い、重い思いがひとつの新しいいのちとなって舞い降りてくる。仏教の輪廻転生のような、いのちの円環を追う温かい視線がある。「ベッドのうえに横たわるきみの/豊かでたおやかなおなかの稜線が/初々しいいのちで/ときどき揺れている//はぴばあすでい」。いろんな人々との別れを経て、やっとたどり着いた小さないのちが、尊いものでないはずがない。
姜運/「木曜日」
街のみんなは、まるで遊泳しているような「ひんやりと 起伏のない顔」でいるが、話者な傷つきやすく、「鬼」を恐れている。「鬼」とはなにか。きっと、他人(同僚や上司、お客さんなど)とのトラブルの象徴だろう。たとえば、相手を「鬼」に変えないために、言葉遣いに気をつけて(「硬い子音を使ってはいけない/うそ すそ つそ ぬそ/口にしてしまうと鬼が形を持ってしまうから」)、「鬼」を忘れるために食事をして(「950円プラス140円プラス376円」)、帰宅する(逃げる)ためにバスや電車に乗る(「210円プラス205円プラス110円」)。水曜日は折り返し地点、金曜日は週末への期待に満ちているが、間の木曜日はしんどい。そんなサラリーマンの一日のような、ちょっと不思議な作品。